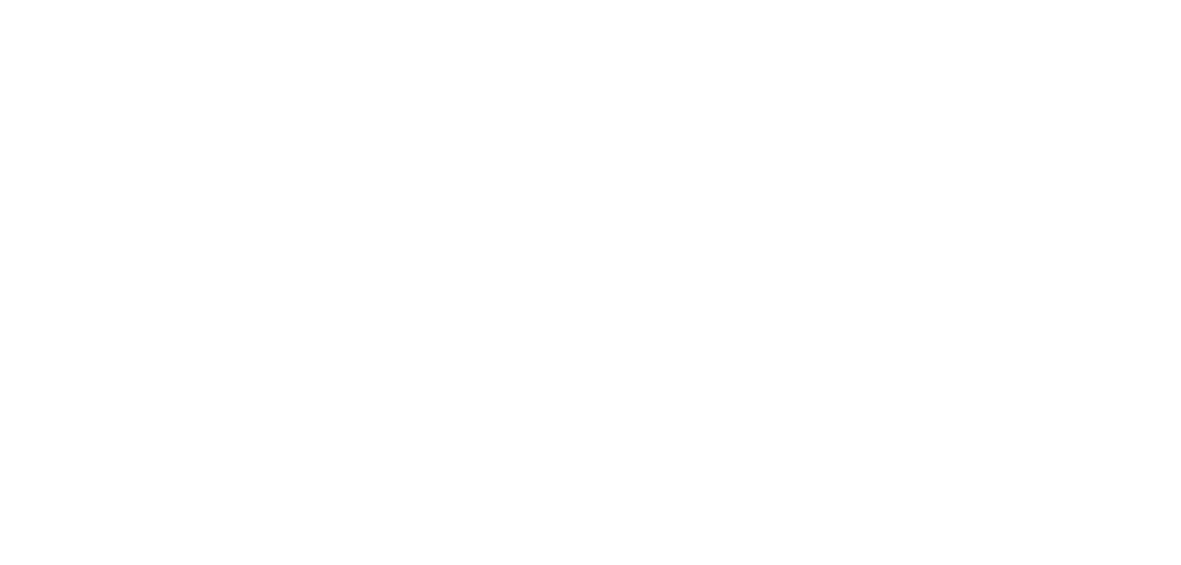ヨガの練習を深めていくと、ポーズ(アーサナ)や呼吸法(プラーナヤーマ)だけでなく、心の働きについて深く考察する教えに出会います。その中心にあるのが、『ヨーガスートラ』です。『ヨーガスートラ』は、ヨガの根本経典であり、古代インドの賢者パタンジャリによって編纂されたとされています。
『ヨーガスートラ』は、私たちが日々の生活の中で感じる様々な苦しみ、悩み、そして生きづらさの根本原因を「クレーシャ」という概念で説明しています。クレーシャは、日本語では「煩悩」や「苦」と訳されることもありますが、単なる苦しみではなく、私たちの心を曇らせ、真実を見えなくする根本的な原因を指します。
この記事では、『ヨーガスートラ』が説く五種類のクレーシャ(五煩悩)について、その定義、具体的な現れ方、そしてそれらを克服するためのヨガの実践について、深く掘り下げていきます。東洋思想の歴史的な流れを汲みながら、現代を生きる私たちにとって、クレーシャの理解がどのように役立つのかを考えていきましょう。
もくじ.
クレーシャとは何か? – 心の苦しみの根源
クレーシャ(kleśa)は、サンスクリット語で「苦悩」「煩悩」「汚染」などを意味する言葉です。『ヨーガスートラ』では、クレーシャは私たちの心が本来持っている純粋な状態を覆い隠し、真実の自己(プルシャ)を認識することを妨げる根本原因とされています。
東洋思想、特にインド哲学の文脈では、私たちの本質は純粋で、至福に満ちた存在であると考えられています。しかし、現実には多くの人が苦しみや悩みを抱えて生きています。このギャップを生み出しているのが、クレーシャなのです。
クレーシャは、単なる一時的な感情や思考パターンではなく、私たちの心の奥深くに根ざした、無意識の領域にまで及ぶものです。そのため、クレーシャを克服することは容易ではありませんが、ヨガの様々な実践を通じて、徐々にその影響を弱め、最終的には完全に取り除くことができると『ヨーガスートラ』は説きます。
五種類のクレーシャ – 無知から始まる苦しみの連鎖
『ヨーガスートラ』では、クレーシャは以下の五種類に分類されています。
-
アヴィディヤー(avidyā):無知、無明
アヴィディヤーは、他のすべてのクレーシャの根源となるものです。ここでいう無知とは、単に知識がないことではなく、自己の本質や世界の真実についての根本的な誤解を指します。具体的には、「私」という個別の存在が実体であると信じ込み、永遠に変化しない自己があると思い込むことです。
東洋思想では、この世界は常に変化し続けるものであり、固定的な実体は存在しないと考えられています(無常)。しかし、私たちは無意識のうちに、「私」という意識を固定化し、それに執着してしまうのです。この根本的な誤解が、他のすべての苦しみを生み出す原因となります。
-
アスミター(asmitā):自我意識、個体意識
アスミターは、アヴィディヤーから生じる、自己と他者を区別する意識です。「私」という感覚は、本来、純粋な意識(プルシャ)と、心や体といった物質的な要素(プラクリティ)が混同されることによって生じます。
アスミターは、私たちが社会生活を送る上で必要なものではありますが、過剰になると、自己中心的な考え方や行動につながり、他人との比較、優越感、劣等感といった感情を生み出します。
-
ラーガ(rāga):執着、貪欲
ラーガは、快楽や喜びをもたらす対象に対する強い執着です。過去の快楽の記憶に基づいて、「あれが欲しい」「これがしたい」という欲望が生まれます。
ラーガの問題は、快楽が一時的で、必ずしも私たちを幸福にしないことです。欲望が満たされても、すぐに次の欲望が現れ、心が満たされることはありません。また、執着が強すぎると、対象を失った時に大きな苦しみを感じることになります。
-
ドヴェーシャ(dveṣa):嫌悪、憎しみ
ドヴェーシャは、ラーガの反対で、苦痛や不快感をもたらす対象に対する強い嫌悪や憎しみです。過去の不快な経験に基づいて、「あれは嫌だ」「これは避けたい」という感情が生まれます。
ドヴェーシャは、私たちを苦しみから遠ざけるための自然な反応ですが、過剰になると、怒り、敵意、攻撃性といった感情を生み出し、人間関係を悪化させたり、自分自身を傷つけたりすることにつながります。
-
アビニヴェーシャ(abhiniveśa):死への恐怖、生存本能
アビニヴェーシャは、死への恐怖、そして生への強い執着です。これは、すべての生物に共通する本能的なものであり、自己保存のために必要なものです。
しかし、アビニヴェーシャが過剰になると、変化を恐れ、新しいことに挑戦することを避け、現状にしがみつくようになります。また、死への恐怖が強すぎると、常に不安や恐怖に苛まれ、人生を十分に楽しむことができなくなります。
クレーシャの相互関係 – 苦しみの連鎖を断ち切る
五種類のクレーシャは、それぞれが独立して存在するのではなく、互いに密接に関連し合っています。アヴィディヤー(無知)を根源として、アスミター(自我意識)、ラーガ(執着)、ドヴェーシャ(嫌悪)、アビニヴェーシャ(死への恐怖)が生じ、これらが複雑に絡み合うことで、私たちの苦しみは増幅されていきます。
例えば、
-
「私」という感覚(アスミター)が強い人は、自分の意見や立場に固執し(ラーガ)、それに反対する人を嫌悪する(ドヴェーシャ)傾向があります。
-
過去の成功体験に執着する(ラーガ)人は、変化を恐れ(アビニヴェーシャ)、新しい挑戦を避けるかもしれません。
-
健康への過度な執着(ラーガ)は、老いや病気への恐怖(アビニヴェーシャ)を強める可能性があります。
このように、クレーシャは互いに影響し合い、私たちの心を複雑に絡めとっていきます。この連鎖を断ち切るためには、まず根本原因であるアヴィディヤー(無知)を克服することが重要です。
ヨガの実践によるクレーシャの克服
『ヨーガスートラ』は、クレーシャを克服し、心の苦しみから解放されるための具体的な方法として、八支則(アシュタンガ・ヨガ)と呼ばれる八つの段階のヨガの実践を提示しています。
-
ヤマ(Yama):禁戒 – 社会生活における倫理的な行動規範(非暴力、正直、不盗、禁欲、不貪)
-
ニヤマ(Niyama):勧戒 – 個人生活における内面的な規律(清浄、知足、苦行、読誦、神への献身)
-
アーサナ(Asana):坐法 – 安定した快適な姿勢
-
プラーナヤーマ(Pranayama):呼吸法 – 呼吸のコントロール
-
プラティヤハーラ(Pratyahara):制感 – 感覚の制御
-
ダーラナ(Dharana):集中 – 心を一箇所に集中させること
-
ディヤーナ(Dhyana):瞑想 – 集中が深まり、途切れることなく持続する状態
-
サマーディ(Samadhi):三昧 – 瞑想が深まり、自己と対象が一体化した状態
八支則の実践は、段階的に進められ、最終的にはサマーディ(三昧)と呼ばれる、自己と宇宙が一体化した至高の意識状態に至ることを目指します。
八支則の初期段階であるヤマとニヤマは、日常生活における倫理的な行動や内面的な規律を整えることで、クレーシャの影響を弱める土台を作ります。アーサナとプラーナヤーマは、身体と呼吸を整えることで、心を安定させ、集中力を高めます。プラティヤハーラ、ダーラナ、ディヤーナは、心の働きを制御し、瞑想を深めることで、クレーシャの根本原因であるアヴィディヤー(無知)を克服するための準備をします。
現代社会におけるクレーシャの理解と克服
『ヨーガスートラ』が説くクレーシャの概念は、古代インドの思想に基づいていますが、現代社会を生きる私たちにとっても、非常に重要な意味を持っています。
現代社会は、情報過多、競争社会、ストレス社会など、様々な要因によって、私たちの心は常に揺れ動き、クレーシャが生じやすい状況にあります。SNSでの「いいね!」の数に一喜一憂したり、他人との比較で劣等感を感じたり、将来への不安に押しつぶされそうになったりすることは、誰にでもある経験でしょう。
しかし、クレーシャのメカニズムを理解し、ヨガの実践を通じて、心の働きを観察し、コントロールすることを学ぶことで、私たちはこれらの苦しみから解放される可能性を手にすることができます。
例えば、
-
SNSでの反応に過度に執着しない(ラーガの抑制)
-
他人との比較をやめ、自分の内面的な成長に目を向ける(アスミターの緩和)
-
将来への不安を受け入れ、今この瞬間に集中する(アビニヴェーシャの克服)
といった具体的な行動は、ヨガの実践を通じて培われる心の力によって、より容易に実践できるようになります。
まとめ – クレーシャの克服は、真の自己への道
『ヨーガスートラ』が説く五種類のクレーシャは、私たちの心の苦しみの根本原因であり、真実の自己を認識することを妨げるものです。しかし、クレーシャのメカニズムを理解し、ヨガの実践を通じて、心の働きを観察し、コントロールすることを学ぶことで、私たちはこれらの苦しみから解放され、より自由で、より満たされた人生を送ることができるようになります。
クレーシャの克服は、決して容易な道のりではありません。しかし、それは、私たちが本来持っている純粋な意識、真実の自己(プルシャ)へと至るための、かけがえのない道なのです。
この記事が、あなたのヨガの練習を深め、クレーシャの克服への道のりを歩むための一助となれば幸いです。
ヨガの基本情報まとめの目次は以下よりご覧いただけます。