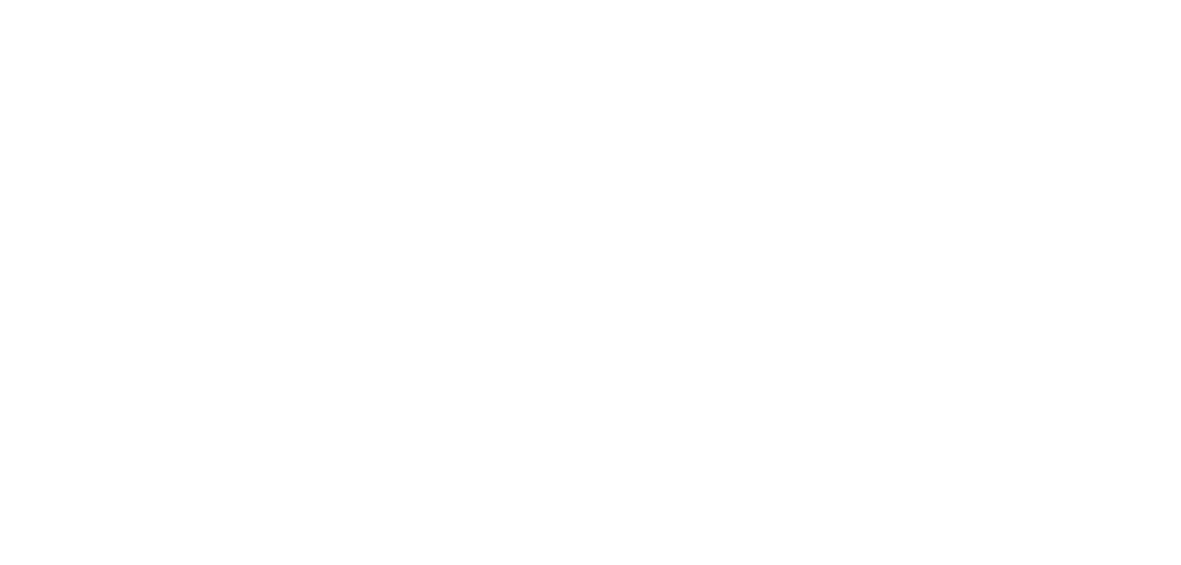ヨガの根本的な教典にヨーガスートラというものがあります。現代でも読むことができます。紀元前200年頃に成立された書物です(成立時期には諸説あります)。これだけでも凄いことに思えますよね。
ヨガの教典には大きく二つあるとされております。こちらのヨーガ・スートラとバガヴァッド・ギーターです。
ヨーガスートラにアシュタンガヨガというヨガの八支則というのが出てきます。
パタビ・ジョイスさんが考案された流派としてのアシュタンガヨガとは異なりますのでご注意ください。
ヨガの八支則についてご存知のない方は、まずはこちらを読んでざっくりと理解をお願いします。
もくじ.
ヤマ・ニヤマのおさらい
ヤマは、日常生活においてやってはいけないこと、やらないように気をつけることです。
- アヒンサー:非暴力、暴力を振るわないこと
- サティヤ:正直にし、嘘を言わないこと
- アスティヤ:盗まないこと
- ブラフマチャリヤ:性欲、睡眠欲、食欲を制御すること
- アパリグラハ:必要以上に貪らないこと
ニヤマは、進んで実行すること、やった方がよいことですね。
- シャウチャ:清潔にすること、清潔さを保つこと
- サントーシャ:足るを知ること、知足
- タパス:苦しみや苦難を受け入れること
- スワディヤーヤ:ヨガの教典を学ぶこと
- イーシュヴァラ・プラニダーナ:神への献身、目の前にあるあらゆること・起こること全てに身をゆだねること
全体を見てみると、昨今の自己啓発書などでも書いてある内容もありますよね。
ヤマ・ニヤマを生活に取り入れていくことで、なによりも自分自身が楽になることを実感されることでしょう。
徹底的にやる必要はありませんよ。
むしろ、そんなに頑張るものでもありませんので、あなたが納得した範囲でやってみてください。
気になる項目から試してみてくださいね。
ヤマ・ニヤマを実践すると自分を好きになる
ヤマ・ニヤマの実践は自分を好きになるという効用があります。
ヤマであれば、アパリグラハ(貪らないこと)を実践していくと、心が安定していきますし、欲に溺れて常に渇望状態となって「ないない」という思いからも離れていきます。
そういった欲から離れていき、自分自身が落ち着いてくると、冷静に自分を見ることができ、自分を愛おしく感じていくものです。「わたしも、よくやっているな」という感覚かもしれません。
そのようにして、ひとつひとつを実践していくと自分を好きになっていきます。
ポイントは、自己評価が高まるということに思います。
実際にやってみるとわかります。自己評価が高まるのですね。
だから自然と生活も楽になります。
生活のなかで、ずっと一緒にいるのが自分ですからね、その自分が楽になると一日が楽になります。
ヤマ・ニヤマを生活に取り入れていくことで、楽になってみてください。頑張らなくていいので。
ヤマ・ニヤマを実践するとセルフイメージが上がる
ヤマ・ニヤマの実践はセルフイメージを高めるのにも有効に感じます。
自己啓発のようにヨーガスートラを解釈するのは微妙かもしれませんが、実際に効果はあると思います。
セルフイメージは高いですか?低いですか?
セルフイメージが低いと何をするにもビクビクして行動してしまいます。
愛されている感覚も低いかもしれません。自分自身を自分で低く設定していると、それに見合った物事が起こるようにできています。
だから、セルフイメージは高く持っておくといいでしょう。
闇雲に高く設定したところで、ただのイメージで終わってしまうので、行動をするといいと思います。
それが、ヤマ・ニヤマなのだと思います。
ヤマから始めるのがいいかもしれません。
今やっていることにプラスするのは習慣を変えるのも大変なので、やってしまっていることを”やめる”ことからスタートしてみてはいかがでしょうか。
ヤマ・ニヤマを実践すると自信がつく、落ち着きが生まれる、状態が良くなる、肯定的になる、自分を許せる
ヤマ・ニヤマの実践はセルフイメージを高めるだけでなく、自信もついていきます。
ニヤマの実践をしていると頑張ることからも離れていきます。
存在しているだけで素晴らしい、という境地になります。存在の価値を認めることができるのですね。
ヤマニヤマの実践は一見得にならなそうなことも入っています。直接的に自分への見返りもないものもあります。「でも社会にはこういうことをする人が必要だよね」という内容がありますよね。
そういったことを実践することがヤマニヤマになります。
それは、とても大きな自信になります。自分を肯定することができます。直接的に得ではないけど、自らスタートさせたことは自分を認めることになります。自己肯定感が高まるのです。
さきほども書いた「存在の価値を認めること」につながるのです。
母親からの無条件の愛、という言葉に置き換えることもできるでしょう。
このような存在の価値に気づいていくのです。
足るを知る、というのも「すでにある」ということへの気づきにもつながります。
あるのですね。ある。
ありのままに気づいていくのです。
終わりに:倫理観というのは時代で変化する

倫理観というのは時代によって変化します。
だから今倫理的であっても、未来には犯罪に近い振る舞いも多くあると思います。
一昔前なら許されたことが、今では許されないことも多々ありますよね。具体例はここでは挙げませんが。
ヤマ・ニヤマは今の倫理観すると実践できることに思います。
教典の勉強(スワディヤーヤ)は実践しにくいかもしれませんが、インド哲学やヨガに興味があれば、実践できます。
聖者の書かれた書籍でもそれは良いと思います。散々オススメしてきています、ラマナ・マハリシさんの本での勉強も良いと思います。
本当に傑作です。私も読み直してみようと思います。
また、現存している聖者(私が勝手に聖者と判断しています)でムージという方もいらっしゃいます。この方も素晴らしい方で、大変に勉強になります。こういった聖者の本は知識が増えることはないでしょう。知識が増えることが「悟り」には必要ではないからです。
老子の言葉を借りれば、知識ではなく智恵をつけなさい、ということですね。
智恵は捨てることです。
ご参考にされてみてください。
追記:下書きが公開されていたようです
こちらの記事、下書き段階で公開されていたようですね。
すみませんでした。気をつけますね。