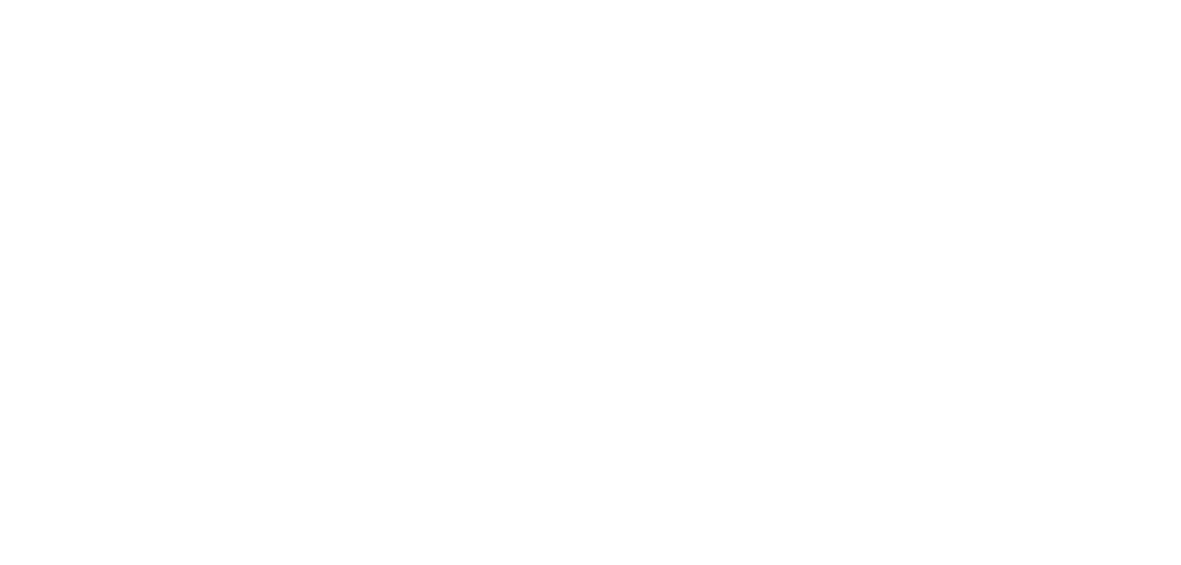私たちは日々、何を、いつ、どのように食べるかという選択を迫られています。その中でも、1日に3食を摂るか、2食にするかという問いは、単なる食事の回数以上の意味を持ち、私たちの身体、心、そして社会との関わり方に深く関わっています。
ここでは、3食を摂ることのメリットや食事回数を減らすことのデメリットについて、ヨガ哲学、東洋思想、そして現代社会の視点から、深く掘り下げていきます。
そもそも、私は2食や1食をやり体調を崩しています。ですので、少し偏った意見にはなります。また、一般的には合う人合わない人もいます。それは生物的な相性とその人のライフスタイルとしての相性を含みます。血糖値や血管年齢、慢性疲労などが気になる人は3食がお勧めです。
3食を摂ることの意義
1.身体の恒常性維持とエネルギー供給
私たちの身体は、常に変化する外部環境に適応しながら、内部環境を一定に保とうとする「恒常性(ホメオスタシス)」という機能を持っています。3食を規則正しく摂ることは、血糖値の急激な変動を抑え、インスリンの過剰な分泌を防ぎ、身体の恒常性維持に貢献します。
-
エネルギーの安定供給: 脳や筋肉などの活動に必要なエネルギーを持続的に供給し、集中力やパフォーマンスの維持をサポートします。
-
血糖値の安定: 食事の間隔が空きすぎると血糖値が乱高下しやすくなりますが、3食を摂ることで血糖値の変動を緩やかにし、身体への負担を軽減します。
-
消化器系の負担軽減: 一度に大量の食事を摂ると消化器系に負担がかかりますが、3食に分けることで消化吸収を円滑に進めることができます。
2.心の安定と社会的リズムの形成
食事は単なる栄養補給の手段ではなく、心と身体を繋ぐ大切な行為です。3食を規則正しく摂ることは、心の安定をもたらし、社会的なリズムを形成する上でも重要な役割を果たします。
-
精神的な安定: 空腹状態が続くとイライラしたり、集中力が低下したりすることがありますが、3食を摂ることで精神的な安定を保ち、穏やかな気持ちで過ごすことができます。
-
セロトニンの分泌促進: 食事を摂ることで、幸福感をもたらす神経伝達物質であるセロトニンの分泌が促進され、心の健康をサポートします。
-
社会的リズムの形成: 家族や友人との食事を通してコミュニケーションを深め、社会的な繋がりを育むことができます。また、食事の時間を共有することで、生活リズムが整い、規則正しい生活を送ることができます。
3.ヨガ哲学における3食の捉え方
ヨガ哲学では、食事は身体と心の健康を維持するための重要な要素と考えられています。適切な食事は、心身のバランスを整え、内なる平和へと導くための第一歩となります。
-
3つのグナ(性質)の調和: ヨガ哲学では、自然界には3つのグナ(性質)が存在すると考えられています。
-
サットヴァ(純粋性): 知性、調和、幸福をもたらす性質。
-
ラジャス(激性): 活動、情熱、変化をもたらす性質。
-
タマス(惰性): 無気力、停滞、無知をもたらす性質。
3食をバランス良く摂ることは、これらのグナの調和を促し、心身の安定に繋がると考えられています。
-
-
アーユルヴェーダの視点: アーユルヴェーダ(インド伝統医学)では、個人の体質(ドーシャ)に合わせて食事を摂ることが重要視されます。3食を基本とし、それぞれの体質に合った食材や調理法を選ぶことで、心身のバランスを整え、健康を維持します。
2食にすることの潜在的なデメリット
近年、健康やライフスタイルの変化から、1日2食という選択をする人も増えています。しかし、2食にすることは、いくつかの潜在的なデメリットも孕んでいます。
1.栄養バランスの偏りと筋肉量の低下
1日の食事回数が減ることで、必要な栄養素を十分に摂取することが難しくなり、栄養バランスが偏る可能性があります。
-
必須栄養素の不足: ビタミン、ミネラル、食物繊維などの必須栄養素が不足しやすくなり、身体機能の低下や免疫力の低下を招く可能性があります。
-
筋肉量の低下: 特にタンパク質の摂取量が不足すると、筋肉量の低下に繋がり、基礎代謝の低下や体力低下を引き起こす可能性があります。
-
骨密度の低下: カルシウムやビタミンDの摂取不足は、骨密度の低下を招き、骨粗鬆症のリスクを高める可能性があります。
2.消化器系の機能低下と便秘
食事の間隔が空きすぎると、消化器系の機能が低下し、便秘などの消化器系の不調を引き起こす可能性があります。
-
消化酵素の分泌低下: 食事の間隔が空きすぎると、消化酵素の分泌が低下し、消化不良を引き起こす可能性があります。
-
腸内環境の悪化: 食物繊維の摂取不足は、腸内環境を悪化させ、便秘や下痢などの消化器系の不調を引き起こす可能性があります。
-
胆汁酸の蓄積: 食事の間隔が空きすぎると、胆汁酸が胆嚢に蓄積し、胆石のリスクを高める可能性があります。
3.社会的孤立と食文化の喪失
食事は単なる栄養補給の手段ではなく、社会的な交流や文化的な伝承の場でもあります。2食にすることで、これらの機会が失われる可能性があります。
-
家族や友人とのコミュニケーション不足: 家族や友人との食事の機会が減り、コミュニケーション不足に繋がる可能性があります。
-
食文化の喪失: 伝統的な料理や食材に触れる機会が減り、食文化の喪失に繋がる可能性があります。
-
社会的孤立: 外食や会食の機会が減り、社会的な繋がりが希薄になる可能性があります。
4.ヨガ哲学における2食の捉え方
ヨガ哲学では、極端な食事制限は心身のバランスを崩し、精神的な成長を妨げると考えられています。
-
過度な節制は心身の不調を招く: ヨガの行法の一つである断食(ウパヴァサ)は、本来、心身を浄化し、精神的な集中力を高めるためのものです。しかし、過度な節制は心身のバランスを崩し、精神的な成長を妨げる可能性があります。
-
バランスの取れた食事が重要: ヨガでは、アヒムサ(非暴力)の精神に基づき、動物性の食品を避ける菜食主義が推奨されることもありますが、栄養バランスの取れた食事を摂ることが最も重要です。
食事をしない時間を一定時間とることによるオートファジー促進や臓器を休息させる効果もあります。オートファジーは16時間も断食は必要ありませんし、夕飯を早くして朝食を少し遅くするだけでも十分だったりします。
オートファジーは他にも促進するやり方があります。運動もそうです。私はヨガを習慣にしておりますがこれもオートファジーを促進しております。筋トレや水泳などスポーツジムで行えることも多くあります。身近な栄養素ではカカオ・緑茶・赤ワイン・ベリー系など(ポリフェノール)、納豆・きのこ(スペルジミン)、ウコン(クルクミン)などもオートファジーを促進します。
結論:3食を基本とし、個々のライフスタイルに合わせて柔軟に対応する
3食を規則正しく摂ることは、身体の恒常性維持、心の安定、社会的リズムの形成に貢献します。しかし、現代社会においては、個々のライフスタイルや価値観が多様化しており、必ずしも3食にこだわる必要はありません。2食にする場合は、栄養バランスに十分注意し、必要に応じてサプリメントなどを活用すること(サプリが増えない為にも3食を食べたいところ)で、健康を維持することができます。
最も大切なことは、自分の身体と心の声に耳を傾け、自分にとって最適な食事のスタイルを見つけることです。ヨガ哲学の教えを参考に、心身のバランスを整え、より豊かな人生を送るために、食事と向き合ってみましょう。